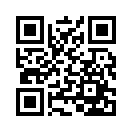2011年11月22日
咳・痰
なぜ咳が出るのでしょうか?
それは、身体の節々を弛め、緊張を解きほぐすためです。
なぜ痰が出るのでしょうか?
それは、肺を掃除するためです。

咳・痰に対するいくつかの処置方法をご紹介していきますので、ぜひ試していただきたいと思います。
<鎖骨窩の温湿布>
咳が止まらないときは、肩が硬張って鎖骨の可動性が悪くなっていますので、鎖骨窩の温湿布を10分間行なってみてください。
左右のうちどちらか硬い方を行ないます。
どちらが硬いかわからない場合は両方(最初に右を5分間、次に左を5分間)に行なってください。
もし左右で硬さが違う場合には、硬い側だけを行なってください。その方が効果的です。

特に、寝て起きてからしばらく咳き込むという場合には効果的です。
鎖骨の可動性が悪いときというのは、肺の脈管運動も悪くなっているのです。
<鼻柱の温湿布>
寝ると咳き込むという場合があります。
これは肺よりも気管の異常から起こるものなのですが、この場合は鼻柱の温湿布を6~10分間行なうとよいです。
咳がひどいときは鼻柱が白っぽくなっていて、触ると冷たくなっています。

そして、その後に脚湯を行なっておくとさらに良いです。

ただし、鼻柱の温湿布と脚湯を同時には行なわないでください。
害になることはありませんが効果が半減してしまいますので、それぞれ別々に行なってください。
<目の温湿布>
熱が出たときもそうですが、咳が出るときも目を休めることが大切です。
目の温湿布を行なうとよいでしょう。
目の神経と呼吸器の神経は重複していて、目を使い過ぎますと呼吸器が刺激を受けて咳が出やすくなってしまうのです。
鎖骨窩の温湿布を行なってから、目の温湿布を行ないますと効果的です。

咳が落ち着くまでは、毎日続けた方がよいでしょう。
風邪をひいて咳が出ているときは、テレビやパソコンや携帯などを見たり、本を読んだりするのはなるべく避けてください。
仕事でどうしても眼を使わなくてはならない人は、なるべく眼の温湿布を行なっておいてください。
特に寝る前に行なうとよいでしょう。
<肘湯>
肘は呼吸器の伸縮に関連していて、肘湯を行いますと胸部の緊張が弛んで呼吸が楽になり、咳が緩和しやすくなります。
例:右の場合

<大腿部後側の硬直を弛める>
大腿部(もも)の裏の筋肉が縮んで硬くなっているので、弛めて伸ばしてあげるとよいです。すると呼吸が楽になります。
方法は、うつ伏せの状態で左右の大腿部(もも)の裏の筋肉を押さえてみて硬く縮んでいる方、または仰向けの状態で足の長さを比べてみて短い方の足を選びます。
選んだ方の足の足首を片手で下から持上げ、軽く抵抗感を感じる高さまで持ち上げていきます。
そしてもう一方の手を膝に当て、グイーッと引き寄せることによって大腿部(もも)の裏の筋肉を伸ばしていきます。
イメージとしては、運動選手が足がつったときによくやっている対処法です。
<水分補給>

咳が完全に抜けるまでは、こまめに飲むようにしてください。
<減食>
咳が落ち着くまでは、なるべく減食をするとよいです。
減食をしなければ炎症はなかなか治まりません。
胃袋がある一定以上に拡がりますと迷走神経が働いて気管に刺激を与えてしまい、咳が抜けきるまで時間がかかってしまうのです。
風邪を治すために、たくさん食べて栄養をつけようとすることは逆効果です。
咳の経過を早めるために、できるだけ減食を行なってください。

<愉気>
咳の経過を促すには、肺の掃除である痰がスムーズにたくさん出てくるようにならないといけません。
頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番に愉気をしますと痰が出やすくなり、咳の経過が促されます。
頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番のポイントですが、顔を下にうつむきますと首の付け根あたりにポコンと突出する骨があります。
それが頸椎7番です。
その上の骨が頸椎6番で、下の骨が胸椎1番ということになります。
人によっては、その突出する骨が頸椎6番だったりすることがあるのですが、とりあえず、その周辺に手を当てて愉気を行なってください。

すると頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番が弛んで可動性が出てきますと痰がたくさん出てくるようになります。
それによって肺の掃除がスムーズに進み、咳をする必要がなくなり、つまり咳が治まってきます。
特に咳がひどいときは頸椎6番の動きが硬く、その場合は頸椎6番を親指で軽く下から押し上げるような感じで愉気をするとよいです。
気が通りやすくなり、頸椎6番が弛みやすくなります。
それからまた改めて、頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番に手を当て愉気を行なってください。
頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番にしばらく愉気を続けていますと、喉がムズムズ・チクチクしてきて咳が出やすくなってしまう
ことがありますが、これは最初だけで、しだいに落ちついてきます。
肺の緊張が愉気によって弛み始めている現象です。
これを通り過ぎますと胸の詰まった感じが弛んで呼吸が楽になり、咳が治まってきますのでご安心ください。
★遠隔でも整体を行なっています。
詳しくはこちらをどうぞ→遠隔整体について
●ご予約のこと、ご質問等ございましたらメールでも受け付けていますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
shizenkenkou@gmail.com
『新潟整体室自然健康堂(野口整体)』
新潟市中央区東大通2-2-9 トーカン万代第二ビューハイツ810
TEL 025-243-0287
それは、身体の節々を弛め、緊張を解きほぐすためです。
なぜ痰が出るのでしょうか?
それは、肺を掃除するためです。

咳・痰に対するいくつかの処置方法をご紹介していきますので、ぜひ試していただきたいと思います。
<鎖骨窩の温湿布>
咳が止まらないときは、肩が硬張って鎖骨の可動性が悪くなっていますので、鎖骨窩の温湿布を10分間行なってみてください。
左右のうちどちらか硬い方を行ないます。
どちらが硬いかわからない場合は両方(最初に右を5分間、次に左を5分間)に行なってください。
もし左右で硬さが違う場合には、硬い側だけを行なってください。その方が効果的です。

特に、寝て起きてからしばらく咳き込むという場合には効果的です。
鎖骨の可動性が悪いときというのは、肺の脈管運動も悪くなっているのです。
<鼻柱の温湿布>
寝ると咳き込むという場合があります。
これは肺よりも気管の異常から起こるものなのですが、この場合は鼻柱の温湿布を6~10分間行なうとよいです。
咳がひどいときは鼻柱が白っぽくなっていて、触ると冷たくなっています。

そして、その後に脚湯を行なっておくとさらに良いです。

ただし、鼻柱の温湿布と脚湯を同時には行なわないでください。
害になることはありませんが効果が半減してしまいますので、それぞれ別々に行なってください。
<目の温湿布>
熱が出たときもそうですが、咳が出るときも目を休めることが大切です。
目の温湿布を行なうとよいでしょう。
目の神経と呼吸器の神経は重複していて、目を使い過ぎますと呼吸器が刺激を受けて咳が出やすくなってしまうのです。
鎖骨窩の温湿布を行なってから、目の温湿布を行ないますと効果的です。

咳が落ち着くまでは、毎日続けた方がよいでしょう。
風邪をひいて咳が出ているときは、テレビやパソコンや携帯などを見たり、本を読んだりするのはなるべく避けてください。
仕事でどうしても眼を使わなくてはならない人は、なるべく眼の温湿布を行なっておいてください。
特に寝る前に行なうとよいでしょう。
<肘湯>
肘は呼吸器の伸縮に関連していて、肘湯を行いますと胸部の緊張が弛んで呼吸が楽になり、咳が緩和しやすくなります。
例:右の場合

<大腿部後側の硬直を弛める>
大腿部(もも)の裏の筋肉が縮んで硬くなっているので、弛めて伸ばしてあげるとよいです。すると呼吸が楽になります。
方法は、うつ伏せの状態で左右の大腿部(もも)の裏の筋肉を押さえてみて硬く縮んでいる方、または仰向けの状態で足の長さを比べてみて短い方の足を選びます。
選んだ方の足の足首を片手で下から持上げ、軽く抵抗感を感じる高さまで持ち上げていきます。
そしてもう一方の手を膝に当て、グイーッと引き寄せることによって大腿部(もも)の裏の筋肉を伸ばしていきます。
イメージとしては、運動選手が足がつったときによくやっている対処法です。
<水分補給>

咳が完全に抜けるまでは、こまめに飲むようにしてください。
<減食>
咳が落ち着くまでは、なるべく減食をするとよいです。
減食をしなければ炎症はなかなか治まりません。
胃袋がある一定以上に拡がりますと迷走神経が働いて気管に刺激を与えてしまい、咳が抜けきるまで時間がかかってしまうのです。
風邪を治すために、たくさん食べて栄養をつけようとすることは逆効果です。
咳の経過を早めるために、できるだけ減食を行なってください。

<愉気>
咳の経過を促すには、肺の掃除である痰がスムーズにたくさん出てくるようにならないといけません。
頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番に愉気をしますと痰が出やすくなり、咳の経過が促されます。
頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番のポイントですが、顔を下にうつむきますと首の付け根あたりにポコンと突出する骨があります。
それが頸椎7番です。
その上の骨が頸椎6番で、下の骨が胸椎1番ということになります。
人によっては、その突出する骨が頸椎6番だったりすることがあるのですが、とりあえず、その周辺に手を当てて愉気を行なってください。

すると頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番が弛んで可動性が出てきますと痰がたくさん出てくるようになります。
それによって肺の掃除がスムーズに進み、咳をする必要がなくなり、つまり咳が治まってきます。
特に咳がひどいときは頸椎6番の動きが硬く、その場合は頸椎6番を親指で軽く下から押し上げるような感じで愉気をするとよいです。
気が通りやすくなり、頸椎6番が弛みやすくなります。
それからまた改めて、頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番に手を当て愉気を行なってください。
頸椎6番・頸椎7番・胸椎1番にしばらく愉気を続けていますと、喉がムズムズ・チクチクしてきて咳が出やすくなってしまう
ことがありますが、これは最初だけで、しだいに落ちついてきます。
肺の緊張が愉気によって弛み始めている現象です。
これを通り過ぎますと胸の詰まった感じが弛んで呼吸が楽になり、咳が治まってきますのでご安心ください。
★遠隔でも整体を行なっています。
詳しくはこちらをどうぞ→遠隔整体について
●ご予約のこと、ご質問等ございましたらメールでも受け付けていますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
shizenkenkou@gmail.com
『新潟整体室自然健康堂(野口整体)』
新潟市中央区東大通2-2-9 トーカン万代第二ビューハイツ810
TEL 025-243-0287