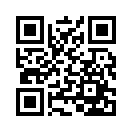2010年12月15日
発熱
どうして熱が出るのでしょうか?

それは、身体が免疫力を高め、体内に入り込んだウイルスやばい菌を煮沸消毒している働きなのです。
また骨格の歪みを整え、筋肉の硬直を弛める目的もあります。
一般的に熱が出ますと冷やして熱を抑え込もうとしますが、野口整体ではその逆で、
熱が出たときは発汗を誘導する処置を行ないます。
発汗によって身体の内側の熱を発散させてあげますと熱が下がりやすいのです。
ということで、ご紹介する処置法は発汗の誘導法ということになります。
熱が出ましたら、38度ぐらいまででしたら、足湯だけでよいです。

先ずは、それで様子をみてください。
身体が温まって身体の節々が弛んできますとそれで熱が下がる場合があります。
ですが、熱が下がらずに逆に上がって以下の体温を越えてきましたら、後頭部の温湿布(後頭部の真ん中、飛び出ている部分に蒸しタオルを当てる)を行なってください。

●大人の場合:38度5分を超えるようでしたら、後頭部を15~40分間。
●子供の場合(3歳以上):39度を超えるようでしたら、後頭部を6分間(~20分間
以内)。
タオルが冷めてきましたらまた熱くして当て、これを数回繰り返します。
すると汗がどんどん出てきて、次第に熱が下がってきます。
発汗によって、熱がそのまま下がる場合と、いったん上がってから一気に下がる場合があります。
後者の場合は、身体がまだ発熱しきっていなかった為に残りの熱によって一時的に
上がるだけですので心配はありません。
その後は急速に下がります。
汗をかくことによって、身体のあちこちにあった歪み・硬張りが弛んでいきます。
汗をかくということは、とても重要な経過なのです。
かいた汗は、こまめに拭いてください。

もし着ている下着などが、汗でしっとりになってきましたら着替えるように努めてください。
汗が皮膚の汗腺をふたのようにしてしまい、更なる汗を出しにくくさせてしまうのです。
また、かいた汗で身体を冷やしてしまいますと、かいた汗を身体が再吸収してしまいます(汗の内攻)
ですので、きちんと汗を拭き取るように心がけてください。
<熱が40度を超えた場合>
もし、熱が40度を超えましたら、鼻柱の温湿布を10分間行ない、その後で小鼻に愉気をしてみてください。

熱が下がりやすくなります。
<熱がなかなか下がらない場合>
熱がなかなか下がらない場合、胸椎7番の1側に愉気をしますと経過が促されます。
それでも、なかなか熱が下がらず不安な時は、とりあえず今回は熱の発散は断念して、額の真ん中の髪の生え際から指3本分上がった部分に「ひよめき」という処があります。
そこを冷たい水で絞ったタオルで冷やしてください。

お願い!:<3歳未満の幼児や60歳以上のご年配の方向けの熱の処理>
熱が出たときの後頭部の温湿布は、3歳未満の幼児や60歳以上のご年配の方、または体力が著しく低下している方には行なわないでください。
高熱を出している状況とは身体にとって必要性があって出ているわけですが、熱を出し
きるにも体力がいるものです。
念のために、あまり体力のない、3歳未満の幼児や60歳以上のご年配の方は無理を
せずに、額の真ん中の髪の生え際から指3本分上がった部分の「ひよめき」という処を
冷たい水で絞ったタオルで冷やしてください。

くれぐれも誤って後頭部を冷やすということだけは絶対にしないでください。
熱が出ている時はいくら動いても構いません。
仕事も学校も休む必要はありません。
ですが、細かい字を凝視したり、パソコンに長時間向かったり、TVを長時間観たりなど、目を酷使するようなことは熱の経過を妨げますので使いすぎないよう心がけてください。
熱は下がってきますと、平熱以下にまで下がる時期があります。
たとえば、36.5度が平熱の人が、36.2度や36度とかにまで下がります。
整体ではこの時期を「安静期」と呼んでいますが、この時期は熱が平熱に戻るまでは、なるべく身体を冷やさないようにして安静に過ごしてください。
熱が出ているときはいくら動いても構いませんが、平熱以下に下がっているこの安静期は心身をゆったりと休ませることが肝要なのです。
この安静期の期間は、個人差もありますが、およそ2時間~半日です。
なるべく安静の時間を確保してください。
この安静期の時期に、「熱が下がったからもう大丈夫」と安心して学校に行かせたり、
仕事に出かけたり、家事を普段どおりにこなしたり、外出したりなどは、できるだけしないようにしてください。
安静期の“安静”の意味ですが、絶対安静でずっと寝ていなければならないというわけではなく、音・光・人・水(冷え)などの過剰な刺激を避けて、心穏やかにして身体を休めるということです。
実際この安静期は、脈も落ち着いてきて、身体は休養を必要としていて、実際に休みたくなるものです。
安静期は退屈かもしれませんが、熱の経過を鈍くさせないために、目を酷使しないよう、テレビを見たり、本を読んだりすることは避け、目を休めるようにしてください。
「安静期」を過ぎて平熱に戻りましたら、今度は起きて平常どおりに動いても大丈夫です。
平熱に戻ったときに、体温を測ってみますとまた平熱よりもちょっと高くなっていることがあり、戸惑う方がいらっしゃいますが、
身体が最後の熱の微調整を行なっているときなので、またすぐに下がります。
心配いりません。
熱が高くなっていく時期というのは実は体力的には充実している時で、逆に熱が下がってきて平温以下になっている時期は、体力が最も消耗している時期なのです。
ですから、この平温以下である「安静期」の時期に無理をしますと身体にとって負担に
なり、身体の自然を乱すことになります。
すると、ダラダラとまた熱が続いてしまったりして却って長引いたりすることがあるのです。
ですが、この「安静期」の時期を穏やかに過ごして経過しますと、身体は軽く顔もスッキリと透明感が出てきます。
そして以前よりも身体の免疫力がレベルアップします。
熱が出ているときは、水分補給をこまめに行なってください。

水分は常温の生水で摂ります。
水分をしっかり摂ることが大切です。
普段、あまり水を飲み慣れていない方は、この調子の悪いときに水を飲むのは飲みづらいようなので、そういう方はスポーツドリンクを水で倍に薄めて飲むとよいでしょう。
そのまま原液で飲みますと糖分が過剰になりますので、水で薄めることをお勧めします。
もし、38度5分以上の熱が3日以上続いて上記の処置を行なっても変化がみられない場合、無理をせずに医療機関を受診することを考慮してください。
症状が出ているときは不安が募るものです。
特に子供さんの場合は、安心する意味も含めまして、いつもと違った異変を感じましたら3日間経たなくても、薬を飲む飲まないは後で考えるとしまして、医者に行くことをお勧めします。
一応の目安ですが、この熱の一連の経過を要する期間は、39度以上の熱が出た場合は4日間ぐらいが標準です。
38度台の熱しか出せない人は1週間くらい、37度台の熱しか出せない人は2週間くらいの経過をとるとみてよいでしょう。
そして、熱が高くなるピークが1回で済んでしまう人は意外と少なく、ピークが2回という場合が多いようです。
風邪をひきこむタイミングというのは身体の重心の偏りが極度になった状態でひきこむことが多いので、その左右の偏り調整として熱の高まりのピークが2回あると思われます。
参考!:発熱したとき、体温経過の観察をするときの目安の為に、日頃の平常時の体温を測って知っておくようにしましょう。
皮膚症状のある方は、この熱の期間に一気に出ることがありますが、熱の経過とともに短期間で終息し、肌がきれいになります。
後頭部の温湿布を行なうには正確なタイミングというものあります。
熱がどんどん上がってきて、もうひとつ熱が上がろうという感じのときに温湿布を行ない
ますと、熱は一気にきれいに下がります。
その正確なタイミングの判断は、発熱の経験を積み重ねていませんと『今だ!』という
見極めはとても難しいと思います。
身体の感じと照らし合わせながら、とりあえずは、上記の体温を目安にして後頭部に
温湿布を当ててみてください。
◎脈を読んで熱の経過を観察する
身体に変動が起きているとき、それが自然な方向への経過なのか、それとも不自然な方向への経過なのか、判別に悩むときがあります。
これを判別する方法として、整体には「一息四脈」の観察法があります。
いろいろなトラブルのときに、その状況を判別することができます。
発熱の場合も、自然な経過に任せてよい熱か、それとも医療機関を受診すべき緊急な深刻な熱かが、判別できますので、覚えておくととても便利です。
皆さんにもできる方法ですので、ぜひ活用していただきたいと思います。
詳しくはこちらをご参考ください→一息四脈
熱が1℃上がりますと脈拍は四つ増えます。
これは自然な熱の状態を意味していますが、逆に脈拍が上っても体温が下がる場合、
これは危険な状態を意味しています。
医療機関を受診することをお勧めします。
その人の身体の状況によって熱の経過の仕方は様々で、なかなかスムーズに経過
しない場合もあります。
そんなとき、不安感が募ってしまうものですが、この「一息四脈」の観察法を使うことに
よって冷静に判断することができます。
安静期を経過して、体温を測って平熱に戻っていたとしても、一息四脈を観察してみて、もし一息四脈以下でしたらまだ安静が必要ですので、ご注意ください。
<熱が上がったり下がったりを繰り返す場合>
胸椎10番という背骨が捻れていますと、熱が上がったり下がったりを繰り返すことがあります。熱の経過をスムーズにするべく胸椎10番の捻れをとる調整として、側腹に愉気をするとよいです。
方法は、左右の側腹をつまんでみて、どちらか硬く分厚くなっている方の側腹をつまんで引っ張るようにしながら愉気をします。
側腹の中でも特に硬直している処を選んで愉気してみてください。
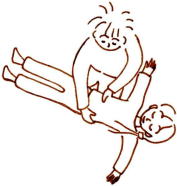
ある程度、弛んできましたら、次は左右の側腹に同時に手を当て、揃えるようなつもりで愉気をしてください。
左右の側腹の柔らかさ、温かさが揃ってきますと胸椎10番の捻れがとれてきて、すると熱が一気に上がり始め、下がりやすくなります。
<熱に変動がみられない場合>
熱がくすぶっていてなかなか変動を起こさないことがあります。
そういう場合、大腿部(もも)の裏の筋肉が縮んで硬くなっているので、弛めて伸ばして
あげるとよいです。
方法は、うつ伏せの状態で左右の大腿部(もも)の裏の筋肉を押さえてみて硬く縮んで
いる方、または仰向けの状態で足の長さを比べてみて短い方の足を選びます。
選んだ方の足の足首を片手で下から持上げ、軽く抵抗感を感じる高さまで持ち上げて
いきます。
そしてもう一方の手を膝に当て、グイーッと引き寄せることによって大腿部(もも)の裏の筋肉を伸ばしていきます。
イメージとしては、運動選手が足がつったときによくやっている対処法です。
すると滞っていた熱に変動が表れ始め、下がりやすくなります。
一般的な熱に対する考え方とは真っ向から逆となりますが、これが野口整体の熱の
経過法です。
決して氷枕のようなもので冷やして無理に熱を下げるというようなことはしないでください。
冷やすということは、身体が一生懸命に体内のウイルスやばい菌を煮沸消毒して良い
方向へ生まれ変わろうとしている作業を中止させ、無理やりに病状を身体の中に吸収
させてしまうということになるのです。
するとその抑え込んだ病状は、いずれ、もっとひどい病気に成長して、本人を苦しめる
ことになります。
身体にとって冷やすということは身体の循環機能を低下させ、鈍化させることになるので、本当によくないことなのです。
熱に対するこのような考え方は他の手技療法や自然療法にもみられます。
また患者さんから聞いた話によりますと、風邪をひいて病院に行ったとき、先生から
「本当は、熱は体力のある証拠なんだから、薬で簡単に止めてはいかん」と言われたことがあるそうです。
そのようにおっしゃる先生はきっと珍しいと思いますが、昔と比べますと少しずつ熱に
対する考え方が変わってきているのかもしれません。
★お付き合いくださり、ありがとうございました・・・感謝しています
整体室のホームページです
http://www.h4.dion.ne.jp/~shizen-k/
《過去のブログ記事を整理して掲載しています》
『新潟整体室自然健康堂(野口整体)』
新潟市中央区東大通2-2-9 トーカン万代第二ビューハイツ810
TEL 025-243-0287
(胎内市でも隔週の日曜日にて活動中)

それは、身体が免疫力を高め、体内に入り込んだウイルスやばい菌を煮沸消毒している働きなのです。
また骨格の歪みを整え、筋肉の硬直を弛める目的もあります。
一般的に熱が出ますと冷やして熱を抑え込もうとしますが、野口整体ではその逆で、
熱が出たときは発汗を誘導する処置を行ないます。
発汗によって身体の内側の熱を発散させてあげますと熱が下がりやすいのです。
ということで、ご紹介する処置法は発汗の誘導法ということになります。
熱が出ましたら、38度ぐらいまででしたら、足湯だけでよいです。

先ずは、それで様子をみてください。
身体が温まって身体の節々が弛んできますとそれで熱が下がる場合があります。
ですが、熱が下がらずに逆に上がって以下の体温を越えてきましたら、後頭部の温湿布(後頭部の真ん中、飛び出ている部分に蒸しタオルを当てる)を行なってください。

●大人の場合:38度5分を超えるようでしたら、後頭部を15~40分間。
●子供の場合(3歳以上):39度を超えるようでしたら、後頭部を6分間(~20分間
以内)。
タオルが冷めてきましたらまた熱くして当て、これを数回繰り返します。
すると汗がどんどん出てきて、次第に熱が下がってきます。
発汗によって、熱がそのまま下がる場合と、いったん上がってから一気に下がる場合があります。
後者の場合は、身体がまだ発熱しきっていなかった為に残りの熱によって一時的に
上がるだけですので心配はありません。
その後は急速に下がります。
汗をかくことによって、身体のあちこちにあった歪み・硬張りが弛んでいきます。
汗をかくということは、とても重要な経過なのです。
かいた汗は、こまめに拭いてください。

もし着ている下着などが、汗でしっとりになってきましたら着替えるように努めてください。
汗が皮膚の汗腺をふたのようにしてしまい、更なる汗を出しにくくさせてしまうのです。
また、かいた汗で身体を冷やしてしまいますと、かいた汗を身体が再吸収してしまいます(汗の内攻)
ですので、きちんと汗を拭き取るように心がけてください。
<熱が40度を超えた場合>
もし、熱が40度を超えましたら、鼻柱の温湿布を10分間行ない、その後で小鼻に愉気をしてみてください。

熱が下がりやすくなります。
<熱がなかなか下がらない場合>
熱がなかなか下がらない場合、胸椎7番の1側に愉気をしますと経過が促されます。
それでも、なかなか熱が下がらず不安な時は、とりあえず今回は熱の発散は断念して、額の真ん中の髪の生え際から指3本分上がった部分に「ひよめき」という処があります。
そこを冷たい水で絞ったタオルで冷やしてください。

お願い!:<3歳未満の幼児や60歳以上のご年配の方向けの熱の処理>
熱が出たときの後頭部の温湿布は、3歳未満の幼児や60歳以上のご年配の方、または体力が著しく低下している方には行なわないでください。
高熱を出している状況とは身体にとって必要性があって出ているわけですが、熱を出し
きるにも体力がいるものです。
念のために、あまり体力のない、3歳未満の幼児や60歳以上のご年配の方は無理を
せずに、額の真ん中の髪の生え際から指3本分上がった部分の「ひよめき」という処を
冷たい水で絞ったタオルで冷やしてください。

くれぐれも誤って後頭部を冷やすということだけは絶対にしないでください。
熱が出ている時はいくら動いても構いません。
仕事も学校も休む必要はありません。
ですが、細かい字を凝視したり、パソコンに長時間向かったり、TVを長時間観たりなど、目を酷使するようなことは熱の経過を妨げますので使いすぎないよう心がけてください。
熱は下がってきますと、平熱以下にまで下がる時期があります。
たとえば、36.5度が平熱の人が、36.2度や36度とかにまで下がります。
整体ではこの時期を「安静期」と呼んでいますが、この時期は熱が平熱に戻るまでは、なるべく身体を冷やさないようにして安静に過ごしてください。
熱が出ているときはいくら動いても構いませんが、平熱以下に下がっているこの安静期は心身をゆったりと休ませることが肝要なのです。
この安静期の期間は、個人差もありますが、およそ2時間~半日です。
なるべく安静の時間を確保してください。
この安静期の時期に、「熱が下がったからもう大丈夫」と安心して学校に行かせたり、
仕事に出かけたり、家事を普段どおりにこなしたり、外出したりなどは、できるだけしないようにしてください。
安静期の“安静”の意味ですが、絶対安静でずっと寝ていなければならないというわけではなく、音・光・人・水(冷え)などの過剰な刺激を避けて、心穏やかにして身体を休めるということです。
実際この安静期は、脈も落ち着いてきて、身体は休養を必要としていて、実際に休みたくなるものです。
安静期は退屈かもしれませんが、熱の経過を鈍くさせないために、目を酷使しないよう、テレビを見たり、本を読んだりすることは避け、目を休めるようにしてください。
「安静期」を過ぎて平熱に戻りましたら、今度は起きて平常どおりに動いても大丈夫です。
平熱に戻ったときに、体温を測ってみますとまた平熱よりもちょっと高くなっていることがあり、戸惑う方がいらっしゃいますが、
身体が最後の熱の微調整を行なっているときなので、またすぐに下がります。
心配いりません。
熱が高くなっていく時期というのは実は体力的には充実している時で、逆に熱が下がってきて平温以下になっている時期は、体力が最も消耗している時期なのです。
ですから、この平温以下である「安静期」の時期に無理をしますと身体にとって負担に
なり、身体の自然を乱すことになります。
すると、ダラダラとまた熱が続いてしまったりして却って長引いたりすることがあるのです。
ですが、この「安静期」の時期を穏やかに過ごして経過しますと、身体は軽く顔もスッキリと透明感が出てきます。
そして以前よりも身体の免疫力がレベルアップします。
熱が出ているときは、水分補給をこまめに行なってください。

水分は常温の生水で摂ります。
水分をしっかり摂ることが大切です。
普段、あまり水を飲み慣れていない方は、この調子の悪いときに水を飲むのは飲みづらいようなので、そういう方はスポーツドリンクを水で倍に薄めて飲むとよいでしょう。
そのまま原液で飲みますと糖分が過剰になりますので、水で薄めることをお勧めします。
もし、38度5分以上の熱が3日以上続いて上記の処置を行なっても変化がみられない場合、無理をせずに医療機関を受診することを考慮してください。
症状が出ているときは不安が募るものです。
特に子供さんの場合は、安心する意味も含めまして、いつもと違った異変を感じましたら3日間経たなくても、薬を飲む飲まないは後で考えるとしまして、医者に行くことをお勧めします。
一応の目安ですが、この熱の一連の経過を要する期間は、39度以上の熱が出た場合は4日間ぐらいが標準です。
38度台の熱しか出せない人は1週間くらい、37度台の熱しか出せない人は2週間くらいの経過をとるとみてよいでしょう。
そして、熱が高くなるピークが1回で済んでしまう人は意外と少なく、ピークが2回という場合が多いようです。
風邪をひきこむタイミングというのは身体の重心の偏りが極度になった状態でひきこむことが多いので、その左右の偏り調整として熱の高まりのピークが2回あると思われます。
参考!:発熱したとき、体温経過の観察をするときの目安の為に、日頃の平常時の体温を測って知っておくようにしましょう。
皮膚症状のある方は、この熱の期間に一気に出ることがありますが、熱の経過とともに短期間で終息し、肌がきれいになります。
後頭部の温湿布を行なうには正確なタイミングというものあります。
熱がどんどん上がってきて、もうひとつ熱が上がろうという感じのときに温湿布を行ない
ますと、熱は一気にきれいに下がります。
その正確なタイミングの判断は、発熱の経験を積み重ねていませんと『今だ!』という
見極めはとても難しいと思います。
身体の感じと照らし合わせながら、とりあえずは、上記の体温を目安にして後頭部に
温湿布を当ててみてください。
◎脈を読んで熱の経過を観察する
身体に変動が起きているとき、それが自然な方向への経過なのか、それとも不自然な方向への経過なのか、判別に悩むときがあります。
これを判別する方法として、整体には「一息四脈」の観察法があります。
いろいろなトラブルのときに、その状況を判別することができます。
発熱の場合も、自然な経過に任せてよい熱か、それとも医療機関を受診すべき緊急な深刻な熱かが、判別できますので、覚えておくととても便利です。
皆さんにもできる方法ですので、ぜひ活用していただきたいと思います。
詳しくはこちらをご参考ください→一息四脈
熱が1℃上がりますと脈拍は四つ増えます。
これは自然な熱の状態を意味していますが、逆に脈拍が上っても体温が下がる場合、
これは危険な状態を意味しています。
医療機関を受診することをお勧めします。
その人の身体の状況によって熱の経過の仕方は様々で、なかなかスムーズに経過
しない場合もあります。
そんなとき、不安感が募ってしまうものですが、この「一息四脈」の観察法を使うことに
よって冷静に判断することができます。
安静期を経過して、体温を測って平熱に戻っていたとしても、一息四脈を観察してみて、もし一息四脈以下でしたらまだ安静が必要ですので、ご注意ください。
<熱が上がったり下がったりを繰り返す場合>
胸椎10番という背骨が捻れていますと、熱が上がったり下がったりを繰り返すことがあります。熱の経過をスムーズにするべく胸椎10番の捻れをとる調整として、側腹に愉気をするとよいです。
方法は、左右の側腹をつまんでみて、どちらか硬く分厚くなっている方の側腹をつまんで引っ張るようにしながら愉気をします。
側腹の中でも特に硬直している処を選んで愉気してみてください。
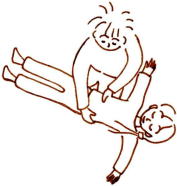
ある程度、弛んできましたら、次は左右の側腹に同時に手を当て、揃えるようなつもりで愉気をしてください。
左右の側腹の柔らかさ、温かさが揃ってきますと胸椎10番の捻れがとれてきて、すると熱が一気に上がり始め、下がりやすくなります。
<熱に変動がみられない場合>
熱がくすぶっていてなかなか変動を起こさないことがあります。
そういう場合、大腿部(もも)の裏の筋肉が縮んで硬くなっているので、弛めて伸ばして
あげるとよいです。
方法は、うつ伏せの状態で左右の大腿部(もも)の裏の筋肉を押さえてみて硬く縮んで
いる方、または仰向けの状態で足の長さを比べてみて短い方の足を選びます。
選んだ方の足の足首を片手で下から持上げ、軽く抵抗感を感じる高さまで持ち上げて
いきます。
そしてもう一方の手を膝に当て、グイーッと引き寄せることによって大腿部(もも)の裏の筋肉を伸ばしていきます。
イメージとしては、運動選手が足がつったときによくやっている対処法です。
すると滞っていた熱に変動が表れ始め、下がりやすくなります。
一般的な熱に対する考え方とは真っ向から逆となりますが、これが野口整体の熱の
経過法です。
決して氷枕のようなもので冷やして無理に熱を下げるというようなことはしないでください。
冷やすということは、身体が一生懸命に体内のウイルスやばい菌を煮沸消毒して良い
方向へ生まれ変わろうとしている作業を中止させ、無理やりに病状を身体の中に吸収
させてしまうということになるのです。
するとその抑え込んだ病状は、いずれ、もっとひどい病気に成長して、本人を苦しめる
ことになります。
身体にとって冷やすということは身体の循環機能を低下させ、鈍化させることになるので、本当によくないことなのです。
熱に対するこのような考え方は他の手技療法や自然療法にもみられます。
また患者さんから聞いた話によりますと、風邪をひいて病院に行ったとき、先生から
「本当は、熱は体力のある証拠なんだから、薬で簡単に止めてはいかん」と言われたことがあるそうです。
そのようにおっしゃる先生はきっと珍しいと思いますが、昔と比べますと少しずつ熱に
対する考え方が変わってきているのかもしれません。
★お付き合いくださり、ありがとうございました・・・感謝しています

整体室のホームページです

http://www.h4.dion.ne.jp/~shizen-k/
《過去のブログ記事を整理して掲載しています》
『新潟整体室自然健康堂(野口整体)』
新潟市中央区東大通2-2-9 トーカン万代第二ビューハイツ810
TEL 025-243-0287
(胎内市でも隔週の日曜日にて活動中)
Posted by 心羽 at 09:56│Comments(0)
│風邪
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。